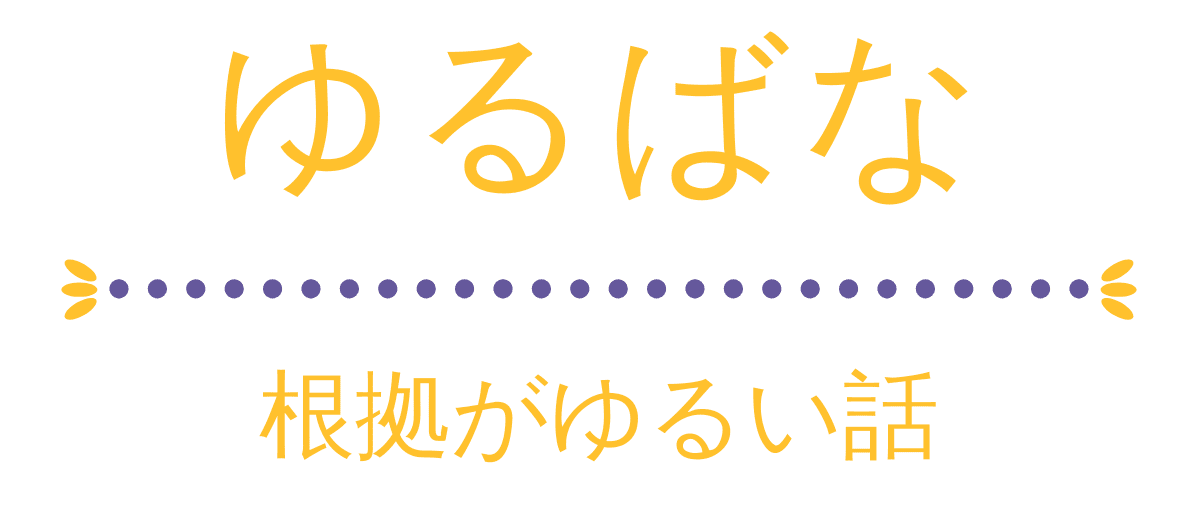今回はまた、根拠があいまいな記事のため「ゆるばな」としてお送りします。
疑問に思ったりした場合は、鵜吞みにせず、自分で調べてねw
昔、日本では、携帯電話とは違う、日本独自の無線電話サービスが存在しました。
それはPHS(ピッチ、パーソナル・ハンディフォン・システムの略)と呼ばれ、中国や台湾でもサービスが開始されました。
PHSは、「固定電話のコードレス電話を屋外に持ち出したときに利用できなくなる」と言う欠点を解消するために誕生した、日本生まれのサービスです。
家でいるときは固定電話の子機、外出中は携帯電話みたいに使える、と言うものです。
ただ、それだと、PHS事業者が儲からなくなるため、次第に携帯電話的な売り方にシフトしていきました。
サービスエリアは狭いけど、安い携帯電話みたいな売り方です。
しかし、次第に携帯電話に押され始めました。
元々は、NTTパーソナル、DDIポケット、アステルと3事業者ありました。
はじめに崩壊したのは電力会社系のアステルでした。
まず、東京電力がアステル東京を鷹山と言う謎会社に売却しました。
これに対し、関西電力は、
「東京電力がPHS事業を開始しようと各電力会社に呼びかけたのに、真っ先に撤退するとは無責任すぎる」
と、憤りました。
話はそれますが、後に東京電力は光ファイバー事業をKDDIに売却しました。
このころの東京電力は、他の電力会社も巻き込んでサービスを開始しておきながら、真っ先に売却・撤退すると言う姿勢を見せ、関西電力の不満は高まっていきました。
そして、東日本大震災を迎えるのでした。
話を戻して、次いで、アステル九州がサービス終了。
アステルの全国エリアが崩壊しました(九州がまるまる圏外に…)。
アステル沖縄はウィルコム(旧・DDIポケット)に事業譲渡しました。
(正しくは、アステル沖縄は、ウィルコム沖縄と言う会社を設立し、事業譲渡しました)
そのため、アステル沖縄の利用者は、ウィルコム(DDIポケット)のネットワークで最後まで使えました。
NTTパーソナルもNTTドコモに吸収された後にサービス終了。
結局最後まで残ったのは、ウィルコム(DDIポケット)でした。
そのウィルコム(DDIポケット)ですが、元々はDDI設立の中心人物だった千本 倖生(DDI元副社長)が力を入れていた事業でした。
彼は電電公社(後のNTT)の近畿電気通信局技術調査部長として、大阪に赴任。
通信の自由化(電電公社民営化)が決まると、関西の有力者に
「一緒に通信会社を立ち上げませんか?」
と呼びかけていったそうです。
松下電器(パナソニック)の松下幸之助氏に断られたときは、心が揺らぎましたが、京セラの稲盛和夫氏が興味を持ってくれた時には、手ごたえを感じたそうです。
稲盛氏も
「こんな計画で本当に大丈夫か?」
と疑心暗鬼だったそうですが、
「行けます」
と自信をもって答え、DDI(第二電電、後のKDDI)を共同で創業。
そんな彼が、DDIでの終盤に力を入れたのが、沈みゆくPHSサービス「DDIポケット」だったのです。
NTTドコモが「ドッチーモ」と言う携帯電話とPHSの両方に対応したサービスを提供し、なんとかPHSの延命を画策する中、DDIは携帯電話事業(DDIセルラー、au)がDDIポケットへ協力することはありませんでした。
その理由の1つに、PHSの無線帯域は、auの第3世代携帯電話にとって、ジャマな帯域だった、と言うのもあると思います。
俗に言う携帯電話の2GHz帯(2100MHz、Band 1)ですが、auの2GHz帯はBand 1の中でも、最もPHSの帯域に近いところにあります。
そのためauの2GHz帯の上り電波がPHSにもろに干渉することになります。
ドコモのドッチーモのように1つの端末内にBand 1の携帯電話とPHSを入れることは、技術的に不可能でした。
それは、ゼロ距離で干渉が起こることになるからです。
距離が離れれば、干渉する電波も弱くなりますが、ゼロ距離だとノーガードで接近戦をするようなものです。
激しい打ちあい、ノーガード殺法になりますw
ただ、auの携帯電話はBand 1以外も使えるため、Band 1さえ使わなければ、ドッチーモのような端末の発売も可能になります。
ただ、それでも、PHS機能のない全端末が、Band 1の利用時にはPHSに配慮する必要があり、KDDIとしてはDDIポケットが静かにサービス終了することを願っていたはずです。
(ちなみにauのBand 1の電波はPHSにとって害になりますが、PHSの電波はauのBand 1にとって、害にはならなかったと思われます)
そんなわけで、アステルとNTTパーソナルは営業不振、PHS最大手のDDIポケットも営業不振な上、親会社のKDDIからジャマ者あつかいされてました。
(KDDIポケットへの社名変更はなく、ドメイン「kddipocket.co.jp」を取得した勇者は、空振りに終わったようですw)
しかし、PHSは中国や台湾などに広がったためか、PHSの帯域はBand 39として携帯電話バンドに登録されてます。
また、PHSで使われていたTDD技術は中国が大変気に入ったようで、第3世代携帯電話ではTDS-CDMA(中国独自規格)として利用されてます。
TDS-CDMAの後継規格はTD-LTEで、こちらは国際標準規格で単にLTEとも表記されます。
LTEには携帯電話従来のFDDモードと、PHSで使われていたTDDモードの2つがあると言うことです。
(日本ではWiMAX 2.1やAXGPと言われているものもTD-LTEであり、LTEです)
(ただ、WiMAX 2.1とAXGPは携帯電話ではなくBWA(ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス)として認可されているので、電話としての音声通話はできません)
(ただ、LINEのようにデータ通信としてならできます)
KDDIからうとまれたPHSですが、なんとなくその魂は携帯電話に残ってるように思うし、KDDIも
「DDIポケットを無理に売却しなくても、基地局用地を携帯電話に転用すれば良かったのでは?」
と言う意見があるようです。
昔、「ワイヤレスとモバイルは違う」と言う謎記事があり、当時の僕はひどく疑問に思いました。
この記事では、無線LANなどをワイヤレスと呼び、携帯電話をモバイルと呼んで、携帯電話を褒め称えていました。
しかし、当時(記事発表前後を含む)のアメリカの携帯電話事業者は、社名にワイヤレスとつく会社が多かったのです。
例をあげますと、
- ベライゾン・ワイヤレス
- シンギュラー・ワイヤレス
- AT&Tワイヤレス
- ボイスストリーム・ワイヤレス(→ T-Mobile)
などです。
その後、シンギュラー・ワイヤレスはAT&Tワイヤレスを吸収し、AT&Tモビリティになった上で、AT&Tに吸収されました。
この人の記事は、未来を書いているのであれば正しかったのだけど、当時はワイヤレス優勢の時代だったのです。
また、携帯電話にモバイルと言う単語を使いだしたのは日本で、この使い方はアメリカに逆輸入されました。
元々、携帯電話を表す英語は、セルラーフォンです。
USセルラーと言う携帯電話事業者もありました。
携帯電話事業者に使われる単語に他にも面白いのがありました。
- エアタッチ・コミュニケーションズ(アメリカ)
- KTフリーテル(韓国)
- バーティ・エアテル(インド)
などです。
また、アメリカ発の第2世代携帯電話規格「iDEN」を採用した会社および携帯電話サービスは、ネクステルと呼ばれることもあったようです。
おしまいw